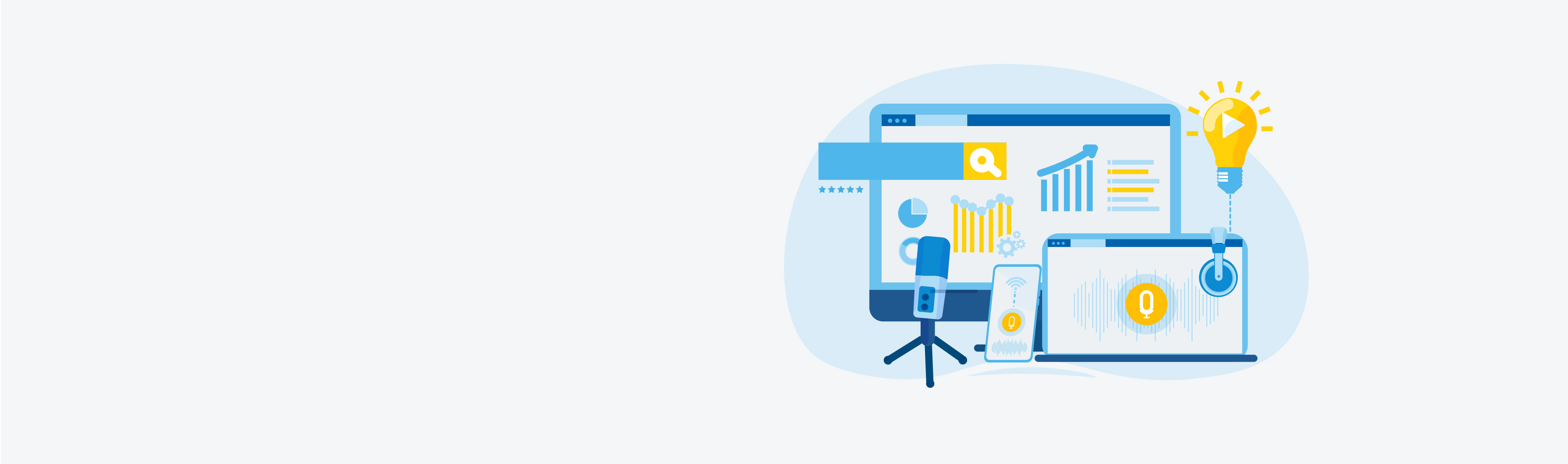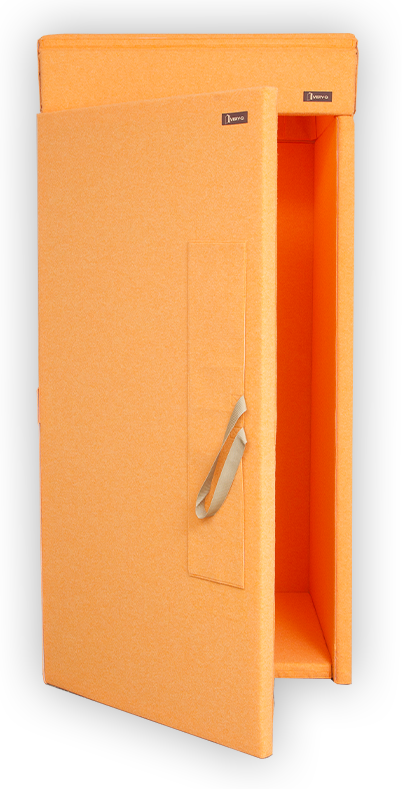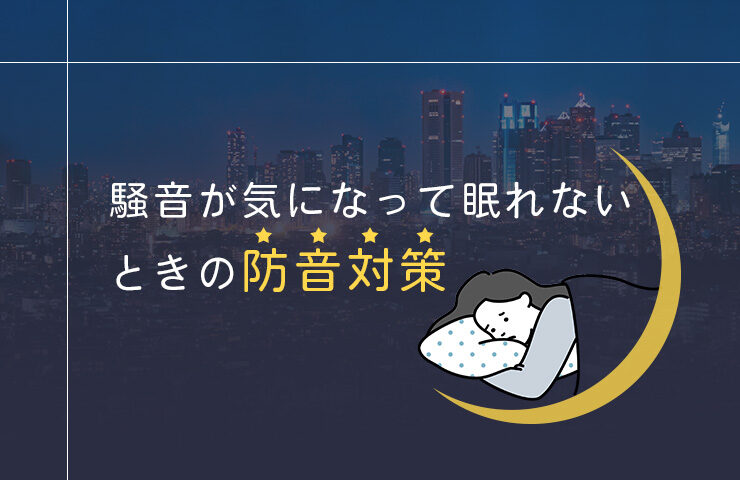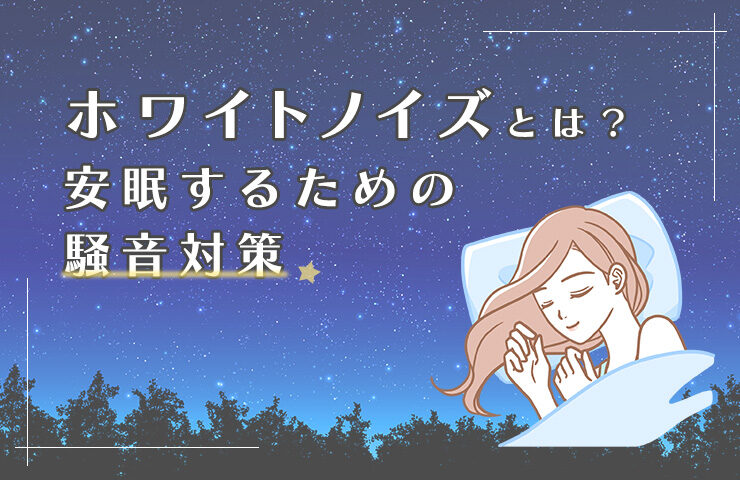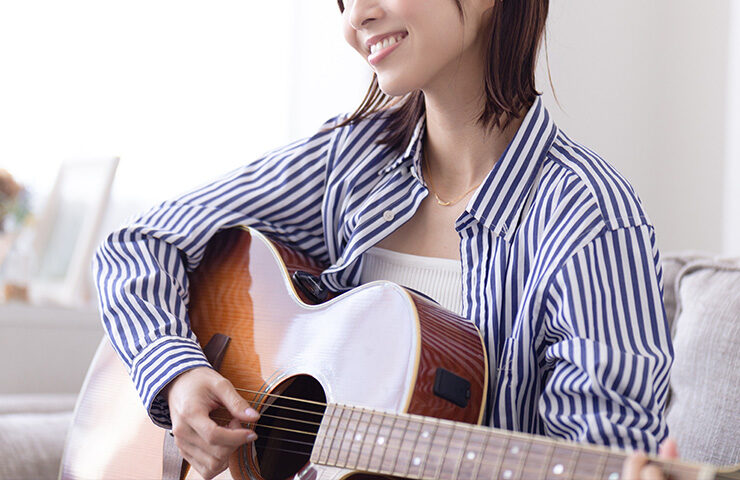手軽に楽しめる! ハーモニカを始めてみよう

小さくて持ち運びやすく、音を出すのも簡単なハーモニカ。初心者でも手軽に始められることから、大人の趣味としても注目を集めています。
見た目以上に奥が深く、演奏スタイルも多彩なハーモニカは、自宅での演奏はもちろん、アウトドアにもおすすめです。
今回は、ハーモニカの魅力や種類、選び方のポイントについて、分かりやすくご紹介します。
幅広い世代に親しまれる「ハーモニカ」の魅力
ハーモニカは、手軽さと味わい深い音色から、長年にわたり親しまれてきた楽器です。
手のひらサイズで持ち運びが簡単で、基本的に穴に直接口をつけて息を吹き込む、または息を吸っただけで音が出るため、初心者でも気軽に取り組みやすいのが最大の魅力となっています。
様々な吹き方を身につければ表現力の幅は非常に奥深く、シンプルな構造ながら多彩な音楽表現が可能です。
音色にはどこか懐かしさがあり、種類によってロックやブルース、フォークやクラシック、童謡や民謡など、幅広いジャンルで使われています。ソロでも十分に楽しめる上、アンサンブルでも活躍できる点も魅力の一つです。
ハーモニカの起源は19世紀初頭のドイツにさかのぼります。発展を続けて19世紀後半にはアメリカへとわたり、ブルースやカントリーの重要な楽器として急速に浸透しました。
日本に初めて輸入されたのは明治時代とされており、戦後には小学校の教育楽器として取り入れられました。
近年では、ハーモニカを愛用している人気ミュージシャンも多く、若い世代にもその魅力が再発見されつつあります。
歴史が深く、幅広い世代に親しまれているハーモニカは、これから楽器を始めたいという方にとって最適な選択肢の一つといえるでしょう。
代表的なハーモニカの種類
ハーモニカには様々な種類があり、演奏スタイルやジャンルに応じて使い分けられています。ここでは、代表的な種類をご紹介します。
・テンホールズハーモニカ(ブルースハープ)
最も広く知られているのが、ダイアトニック・ハーモニカという種類に分類される「テンホールズハーモニカ(ブルースハープ)」です。
その名のとおり10個の穴があり、ブルースやロック、フォークなどのジャンルでハーモニカを使用したい方に人気があります。
吹き口が一列に並んだ形状のシンプルな構造で、手軽に演奏できるのが魅力となっており、それぞれの穴に息を吸い込む、または吹き込むだけで音が出せます。1個の穴を吸った時と吹いた時で、異なる2種類の音を出すことができる仕組みです。
ただし、楽器ごとに決まったキーの音しか出せないため、曲に合わせてハーモニカを持ち替える必要があります。一般的には最初は「C調」が使用される場合が多いので、特に演奏したい曲が決まっていない方におすすめです。
ちなみに「ブルースハープ」は、ドイツの楽器メーカー「ホーナー」の商品名ですが、世界的にベストセラーとなったモデルであるため、テンホールズハーモニカの代名詞となっています。
・クロマチックハーモニカ
ジャズやクラシックでの使用に適しているのが「クロマチックハーモニカ」です。
クロマチックは「半音階」という意味で、側面のスライドレバーを操作することで半音を加える仕組みとなっており、クロマチックハーモニカ1本だけで全ての音階を演奏できます。
そのため、曲のキーによって楽器を持ち替える必要もないのが魅力です。スライドレバーが付いている分、難易度は上がるものの演奏の幅が広がります。
「スライド式ハーモニカ」とも呼ばれていますが、上下に配置された穴で演奏する「上下式」と呼ばれるモデルも存在しています。
・複音ハーモニカ
童謡や懐かしの歌謡曲、演歌などのノスタルジックな音楽を演奏したい方におすすめなのが「複音ハーモニカ」です。
ハーモニカの音を出すのに欠かせない部品の一つが「リード」と呼ばれる小さな金属の板ですが、複音ハーモニカの場合は1つの音に対して2枚のリードを使い、わずかに異なる音程で発音するため、やさしく温かみのある「ゆらぎ」のある音色が特徴です。
楽器ごとに演奏できるキーが決まっているため、曲に合わせてハーモニカを持ち替える必要がありますが、哀愁漂う独特な音色を奏でられるのが魅力となっています。
・教育用ハーモニカ
小学校など教育の現場で使われている「教育用ハーモニカ」は、構造がシンプルで扱いやすいため初心者の方にもおすすめです。最近では大人の入門用としても注目されています。
一般的に使用されている教育用ハーモニカは、ドレミの音階が明確に配置されているのが特徴で、音の出しやすさや軽さ、耐久性などを考慮して作られています。初めてハーモニカに触れるのに最適なモデルといえるでしょう。
ハーモニカ選びのポイントについて

ここでは、ハーモニカ選びの基本的なポイントについて解説します。
・演奏したい音楽ジャンル
まず考えるべきは自分が演奏したい音楽ジャンルです。
ブルースやロックを演奏したいなら「テンホールズハーモニカ(ブルースハープ)」、童謡や演歌を楽しみたいなら「複音ハーモニカ」、より自由な音階でクラシックやジャズに挑戦したいなら「クロマチックハーモニカ」がおすすめです。目的に合った種類を選ぶことで、練習もよりスムーズに進みます。
・使われている素材
ハーモニカの素材には、主にプラスチックや木、金属が使われています。
定番素材の木製は、柔らかい音色が魅力で本格的に始めたい方におすすめです。金属製はパワフルな音を出したい方に適しています。
プラスチック製は丈夫で扱いやすく、少ない息でも音が出せるため、初心者の方におすすめです。
・メーカー
信頼できるメーカーで選ぶこともポイントの一つです。
ハーモニカの代表的なメーカーは、ドイツの老舗「ホーナー」や、国内メーカーの「スズキ」、「トンボ」で、非常に人気があります。
初心者向けからプロ仕様までラインナップが豊富なので、目的に応じて選べるのが魅力です。
自宅で楽器を演奏する際は防音対策を忘れずに!

ハーモニカの魅力や種類、選び方についてご紹介しました。ハーモニカは気軽に音楽の世界へ一歩踏み出せる楽器です。ぜひ焦らずじっくり選び、自分だけのお気に入りを探してみてください。
そして、初心者の方が楽器を始めるにあたって考えておかねばならないのが、練習場所の確保です。
ハーモニカは他の楽器に比べれば音が小さいですが、本格的に始めるのであればしっかりと音を出して練習できる場所が必要です。
一般的には音楽スタジオやカラオケボックス、楽器演奏可能な公共施設などが練習場所によく挙げられますが、専用の「消音器」が付いたハーモニカも販売されており、こうした商品を使えば自宅でも演奏が可能になります。
しかし、あくまで音を軽減するものなので、効果は完全ではありません。
そのため「近隣からの苦情が心配」という方や、「周囲を気にせず演奏したい!」という方には、自宅に防音室を導入して本格的に防音対策するのがおすすめです。
予算やスペースが必要となりますが、防音室があればスタジオなどを借りる必要もなく、いつでも好きな時に楽器演奏を楽しむことができますよ。
また、例えばWeb会議やゲーム、オンラインレッスンなど、仕事や趣味の多種多様な場面で活用できるので、ぜひ検討してみてはいかがでしょうか。
宮地楽器が提供する吸音・消音性抜群の簡易防音室・防音パネルブランド「VERY-Q(ベリーク)」は、多くのプロミュージシャンや楽器演奏を楽しむ方々に導入していただいている実績を活かし、防音対策の新たな形をご提案しております。
防音ボックスや吸音パネルなど、防音対策に便利な製品を多数扱っておりますので、まずはお気軽にお問い合わせ・ご相談ください。