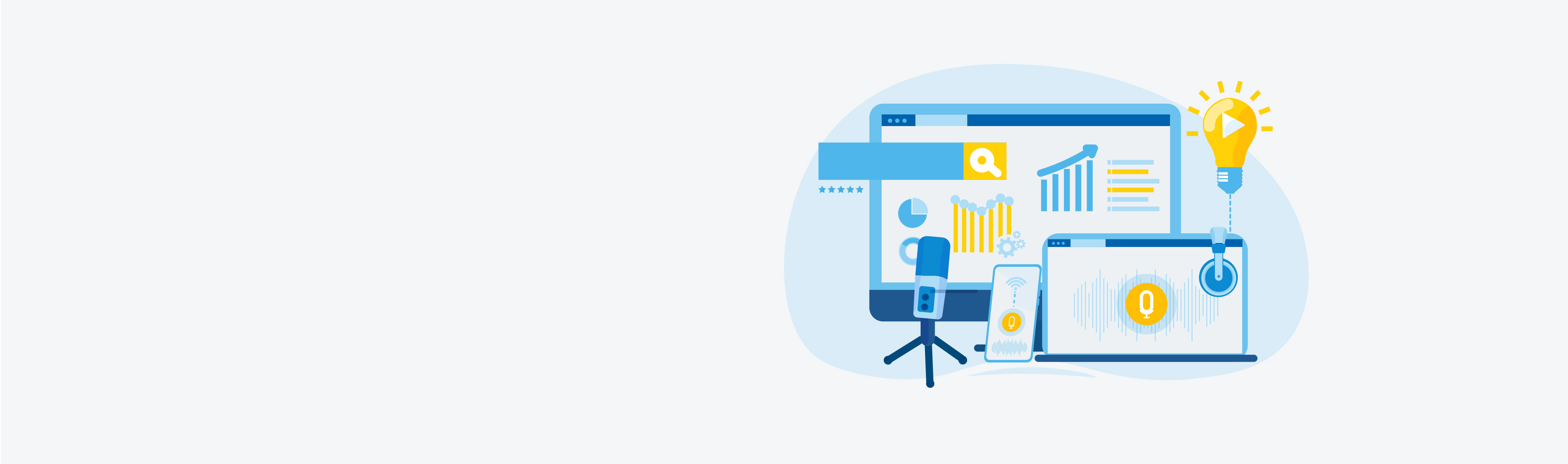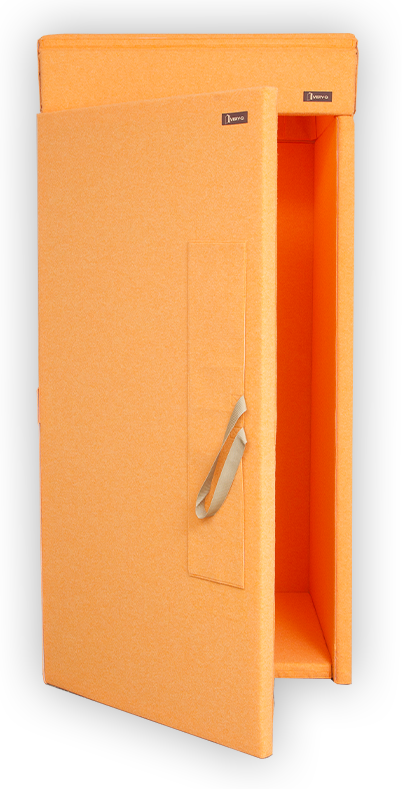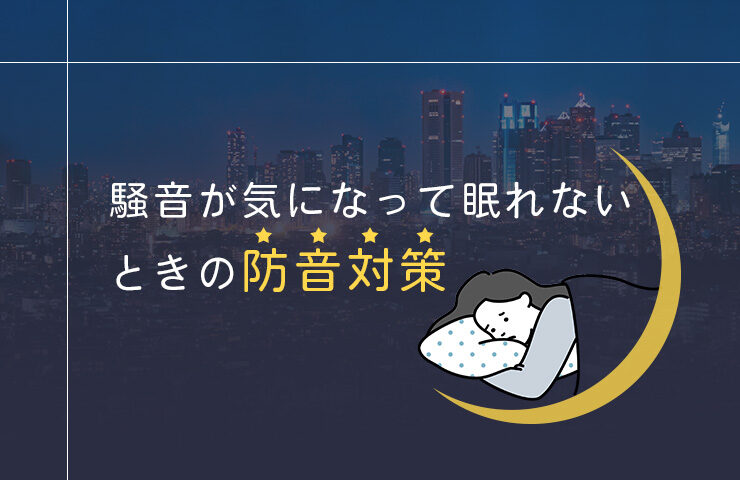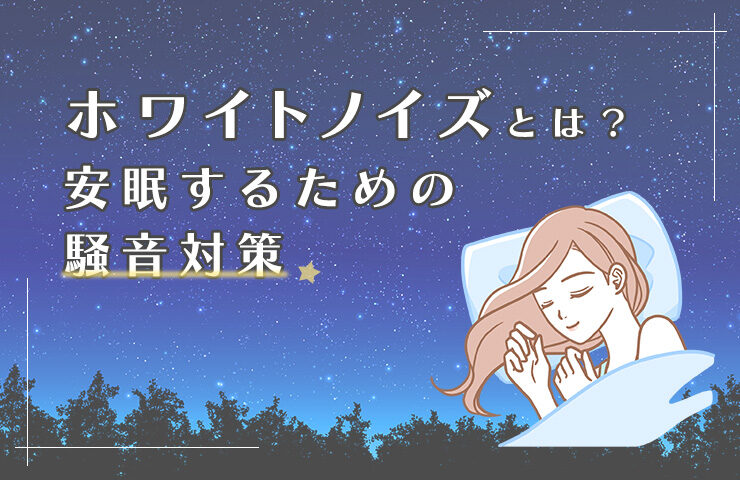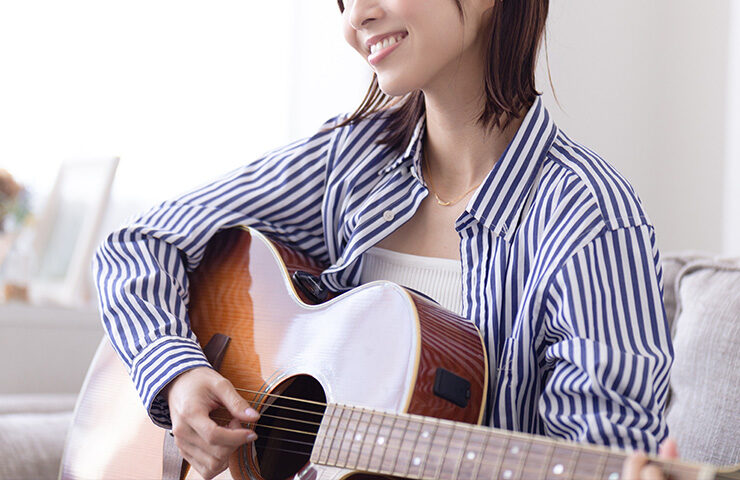世界一難しい楽器?! オーボエをはじめてみよう

「世界一難しい木管楽器」としてギネスブックに登録されているオーボエは、他の管楽器にない独特の澄んだ音色が最大の魅力です。
その美しいメロディに魅了され、「オーボエを始めてみたい!」と思ったことがある方も多いのではないでしょうか? 難しいからこそチャレンジしがいがあり、音が出た瞬間の感動は格別です。
そこで今回は、オーボエの特徴や種類、初心者が楽器を選ぶときのポイントについて分かりやすく解説します。
幅広いジャンルで活躍する「オーボエ」とは?
「オーボエ」は、吹奏楽やオーケストラで独特の存在感を放つ木管楽器のひとつです。その音色は人の声に近いといわれ、温かみがありながらも澄んだ響きを持っています。
演奏会ではチューニングの基準音をオーボエが出すことが多く、楽団の中で大切な役割を担っています。
また、ソロ楽器としてのオーボエもとても魅力的で、クラシック音楽のみならずポップスやジャズ、映画音楽など幅広いジャンルで活躍している楽器です。
オーボエの起源は17世紀のフランスにさかのぼります。元々は「ショーム」という古い楽器から発展し、現在のオーボエの形に近づいていきました。
初期のオーボエはキーの数が少なく、現在のような豊かな音色とはかけ離れたものでしたが、改良されて19世紀ごろからキーの数が増え、多彩な音色で演奏の幅が広がりました。
そして現代では、高度な表現力を持ち、世界中の音楽家に愛される楽器として知られています。
オーボエは「世界一難しい木管楽器」といわれていますが、それはリードの扱いや、繊細な息使いが必要とされるからという点が主な理由となっています。しかし、その難しさを乗り越えて上手く演奏できたときの喜びは格別です。
初心者の方が始めるにはハードルが高く感じるかもしれませんが、挑戦しがいのある楽器といえるでしょう。
オーボエの種類について
オーボエは、指使いや音色に違いがある「ドイツ式」と「フランス式」の2種類に分かれています。これからオーボエを始める方は、まずは世界的に普及しているフランス式を選ぶとよいでしょう。
・ドイツ式
ドイツ式は、オーボエが作られるようになった19世紀ごろに主流となっていたもので、現在はウィーン・フィルハーモニー管弦楽団など、一部のオーボエ奏者が使用しています。別名「ウィンナーオーボエ」とも呼ばれており、一般的には使用されていない特別なオーボエという位置付けになっています。
楽器の上部が膨らんでいるのがドイツ式の大きな特徴です。音色は明るく華やかで、演奏方法は指使いがリコーダーに似ています。
・フランス式
フランス式は19世紀に新しく開発され、現在最も一般的に使われているオーボエです。世界中で製造されているオーボエのほとんどがフランス式であり、初心者の方にもおすすめです。
ドイツ式の不安定な音程を改良したもので、「コンセルヴァトワール・システム」というキーシステムが採用されています。
「コンセルヴァトワール式」とも呼ばれており、指使いがドイツ式に比べてシンプルで、テンポが速い楽曲や難しい楽曲にも対応しやすいため広く普及し、主流となりました。
初心者向けオーボエ選びのポイント

ここでは、初心者向けにオーボエを選ぶポイントについてご紹介します。
・最初の1本には「セミオートマチック」がおすすめ
オーボエは「セミオートマチック」と「フルオートマチック」という2つの方式があり、高い音域を出しやすくするオクターブキーの操作に違いがあります。
セミオートマチックは操作がシンプルで、様々な曲に対応しやすく、軽量でメンテナンスもしやすいため初心者の方におすすめです。初級から上級までモデルも豊富で、世界で広く使用されています。
一方、フルオートマチックは操作は容易ですが、構造が複雑なため調整が難しく、音程が狂いやすいという特徴があるため、最初の1本としてはセミオートマチックを選ぶのが安心です。
・最も一般的な素材は「グラナディラ」
オーボエの素材は主に「グラナディラ」と「ローズウッド」の2種類があります。
最も一般的なのがグラナディラで、ほとんどの木管楽器の素材に使われています。落ち着いた黒い色が特徴となっており、素材そのものの比重が多く、音が遠くに飛ぶという長所があります。広いコンサートホールなどでの演奏に向いています。
ローズウッドは茶色の素材で、華やかで柔らかい音色が特徴ですが、グラナディラほど音が遠くまで響かないため屋内での演奏に適しています。また、湿度や温度の影響を受けやすいので取り扱いに注意が必要です。
そのため、最初の1本にはグラナディラのオーボエを選ぶのがおすすめです。
・メーカーで選ぶのもおすすめ
オーボエは国内外に様々なメーカーがあります。例えば、世界のプロ奏者が愛用しているフランスの「マリゴ」や「リグータ」、入門モデルから上級モデルまで幅広く扱っている国内メーカーの「ヤマハ」などが有名です。
メーカーごとに音色や吹きやすさに特徴があるため、自分に合った楽器を選ぶうえで重要な判断材料の一つになります。
また、オーボエ本体のほかに、ケースやリード、チューナーといった最低限必要なアイテムが一通り揃った「入門セット」を販売しているメーカーもあります。
このように、オーボエ選びのポイントは様々ですので、まずは楽器店で実際に吹き比べてみることが大切です。経験豊富なスタッフに相談しながら、自分に合ったものをじっくり探してみましょう。
自宅に防音室を導入して楽器演奏を楽しもう!

オーボエの魅力や種類、選ぶポイントについてご紹介しました。オーボエは難しいとされる楽器ではありますが、音色に惹かれて挑戦する方も多くいらっしゃいます。
自分に合った1本を見つけて、少しずつ練習を重ねれば、必ず音楽の楽しさが広がっていきますので、まずはオーボエの世界に一歩踏み出してみてはいかがでしょうか。
そして、初心者の方が楽器を始めるにあたって考えておかねばならないのが、練習場所の確保です。一般的には音楽スタジオやカラオケボックス、楽器演奏可能な公共施設のほか、公園や河川敷などが練習場所によく挙げられます。
また、オーボエの場合は、「ミュート(弱音器)」という専用のアイテムを使えば、自宅でも演奏が可能になります。
しかし、あくまで音を軽減するものなので、効果は完全ではありません。
そのため「近隣からの苦情が心配」という方や、「周囲を気にせず演奏したい!」という方には、自宅に防音室を導入して本格的に防音対策するのがおすすめです。
予算やスペースが必要となりますが、防音室があればスタジオを借りる必要もなく、いつでも好きな時に楽器演奏を楽しむことができますよ。
さらに、最近では楽器演奏をスマートフォンのアプリや、ポータブルレコーダーを使用して録音するという方も多く、「ゆくゆくは自宅で録音したい」という場合は防音対策が非常に重要になります。
自宅で録音する場合は、音を鳴らす際に発生する部屋の反響音をマイクが拾ってしまったり、周りの雑音が入ったりしてしまうと音質にも大きく左右するので、クオリティが高い作品作りを行うためにも、防音室の導入を視野に入れておきましょう。
楽器演奏以外にも、例えばWeb会議やゲーム、オンラインレッスンなど、仕事や趣味の多種多様な場面で活用できるので、ぜひ検討してみてはいかがでしょうか。
宮地楽器が提供する吸音・消音性抜群の簡易防音室・防音パネルブランド「VERY-Q(ベリーク)」は、多くのプロミュージシャンや楽器演奏を楽しむ方々に導入していただいている実績を活かし、防音対策の新たな形をご提案しております。
防音ボックスや吸音パネルなど、防音対策に便利な製品を多数扱っておりますので、まずはお気軽にお問い合わせ・ご相談ください。