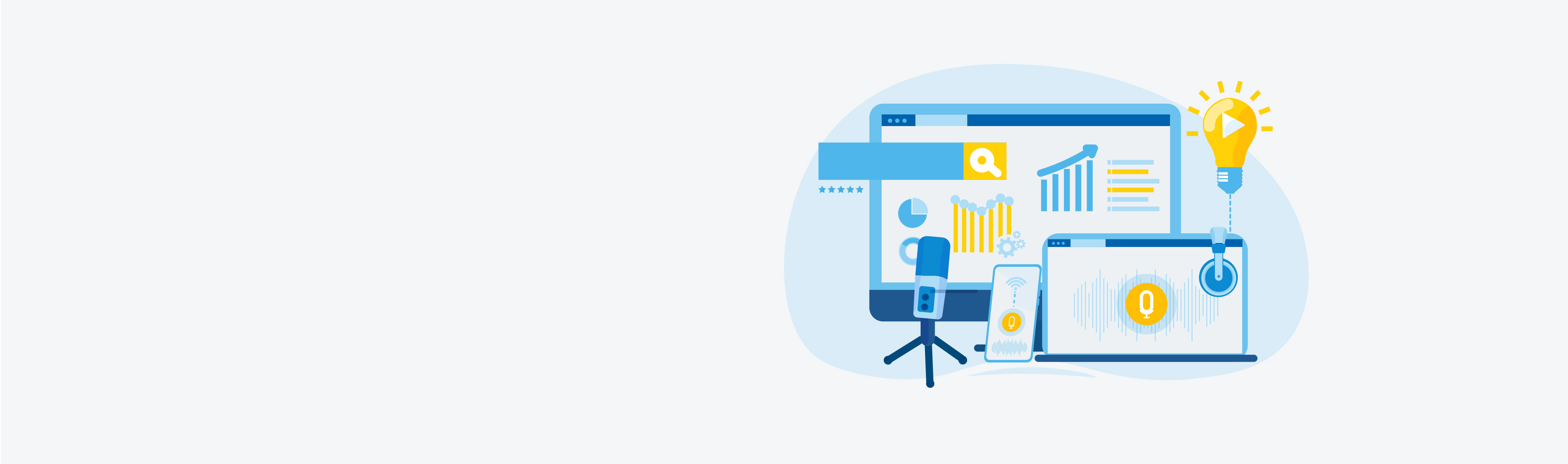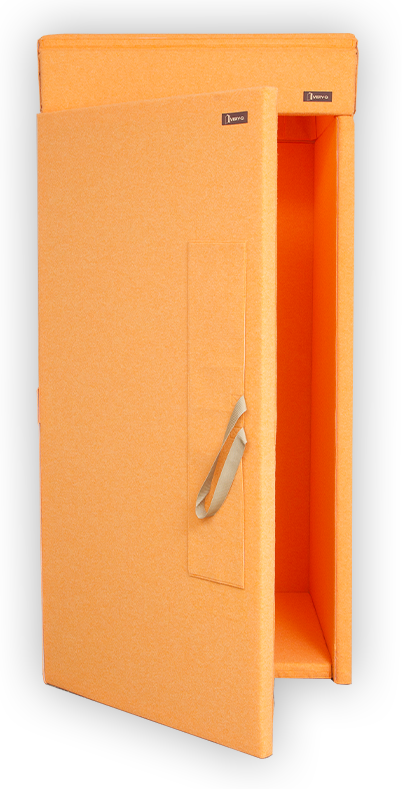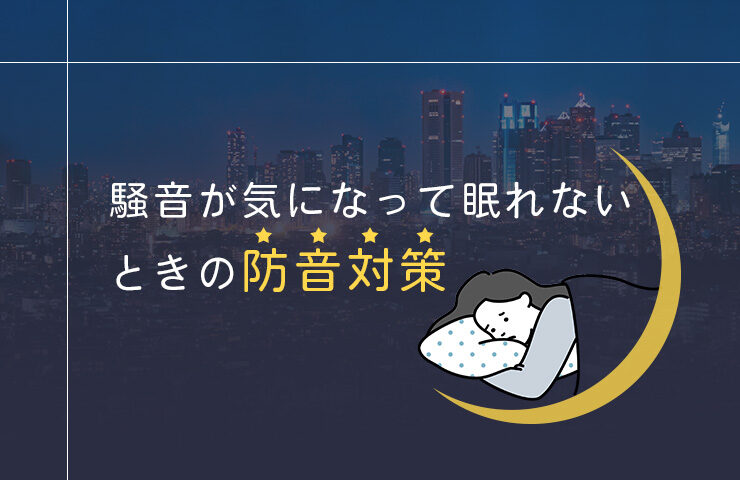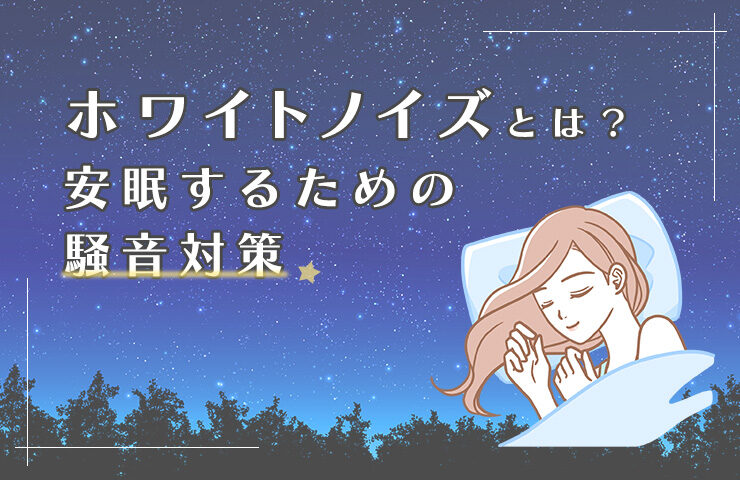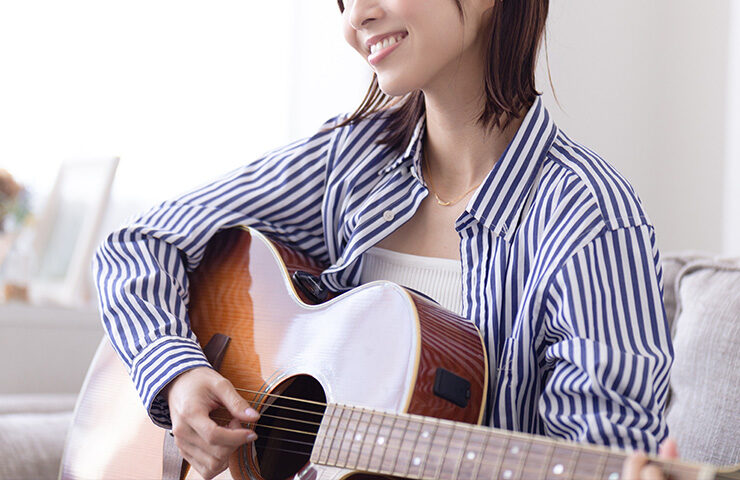防音室を導入する前に知っておきたい注意点について

自宅での楽器演奏やゲームなど、様々な用途で「防音室」を導入するケースが増えています。
防音室は周囲への音漏れを抑えてくれる空間である一方、設置する前にいくつか注意しなければならないポイントがあります。
今回は、防音室を導入してから後悔することがないよう、事前に知っておきたい注意点について分かりやすく解説していきます。
防音室の導入にかかるコスト
防音室を導入する際に最初に考えなければならないのが、「コスト」についてです。
市販されている組み立て式の簡易防音室であれば数十万円程度で購入できますが、本格的に施工するタイプになると数百万円かかる場合もあります。
床や壁に遮音材や吸音材を施工するほか、窓やドアなどにも防音対策を施すためですが、どの程度防音仕様にするかによって価格が大きく異なってきます。
必要な対策だけを施して価格を少しでも抑えるには、どのような用途で防音室を導入するのか明確にしておくことが大切です。
例えば、楽器演奏のためのスペースと、主にWeb会議でのみ使用するスペースでは必要な防音性能の程度が異なるためです。
また、設置費用だけでなくランニングコストも考慮する必要があります。
本格的な防音室は密閉性が高いため、換気システムやエアコン設備を導入する場合があり、その分電気代が高くなる可能性があります。
防音室の設置スペースについて
防音室を導入する際に意外と見落とされやすいのが、設置スペースについてです。
防音室を限られたスペースに設置した場合、部屋全体が狭くなったと感じるケースもあります。
導入前に部屋のレイアウトをしっかりと考え、日常生活に支障が出ないかどうかをシミュレーションしておくことが大切です。床への重量負荷や耐震のチェックも欠かせません。
そして、本格的な防音工事は天井や壁、床に吸音材や遮音材を施工するため、一般的な部屋よりも天井が低くなったり、壁が厚くなったりする場合があります。そのため、思っていたよりも室内が窮屈に感じてしまうかもしれません。狭さが気になる場合は、部分的に防音対策を施す方法もあります。
また、用途によっては楽器や機材などを置くスペースについて考えておく必要があるでしょう。
さらに、狭いタイプの防音室で長時間過ごすと、圧迫感や閉塞感を感じ、楽器の練習に集中しにくくなったり、ストレスとなったりするケースもあります。
特に窓がない防音室の場合は、外の景色が見えず気分転換もしにくいので、長時間利用する際は適度に休憩を挟みましょう。
なお、実際に中に入ったときの感覚を確認するために、導入前にショールームで体験してみることをおすすめします。
防音室は熱や湿気がこもりやすい?
防音室は、隙間を極力減らして気密性を高める構造になっているため、換気がしづらく熱や湿気がこもりやすくなります。
特に夏場は室内の温度が上昇し、汗だくになってしまうことも少なくありません。
さらに、湿気が高くなると部屋にカビや雑菌が発生しやすくなったり、楽器やPCなどの機材を置いている場合は劣化を早めたりする可能性があります。
放置すると不衛生な環境になるだけでなく、健康に悪影響を及ぼすおそれもあるので注意しましょう。
対策としては、エアコンや除湿機、換気扇などを設置するのが効果的です。
その分コストが高くなってしまいますが、熱と湿気の問題によって防音室を使わなくなってしまうというケースもあるため、事前に検討しておきましょう。
防音室の性能や音響に関する問題について

防音室を導入した方の中には、「思ったより防音できていない」と感じるケースがあります。
防音室は組み立て式の簡易的なものから、本格的に施工するタイプまで様々な種類があるので、構造によって防音性能に差が生じます。
そのため、使用する用途や目的に合わせて、どんな性能を求めるのか明確にして選ぶことが重要です。
さらに、「防音室内で音が響きすぎる」という問題が起こる場合もあります。
響きすぎると楽器の場合は、元の音が分からず演奏しにくくなる、音が不快な響きとなり長時間いると苦痛に感じてしまうといった状況につながりかねないため、練習環境としては逆効果です。
また、逆に「吸音しすぎる」というケースもあります。防音室は闇雲に吸音しすぎてしまうと、音の反射が抑えられすぎてしまい、迫力に欠ける不自然な響きになってしまいます。その結果、音は出るけれど響きのない空間での演奏となり、練習のモチベーションが下がる原因にもなるのです。
このように防音対策では、音を周囲に漏らさないだけでなく、防音室内で音響をコントロールする工夫が求められます。
音響についても配慮することで、より理想的な防音対策を実現できるので、まずはどのような音環境を求めているのかを専門業者に相談しましょう。
床の振動にも注意を
防音室を設置する際は、「床から伝わる振動」にも配慮が必要です。
特にマンションやアパートといった集合住宅では、床の振動が原因で下の階に音が響いてしまうことがあります。
ドラムやピアノなど、床面に接した状態で演奏する楽器は、直接床に強い振動を与えるため、防音室に入っていても「ドンドン」という低音や振動音が下階へ伝わりやすいのです。電子ドラムや消音タイプのピアノでも同様です。
また、その他の楽器でも足でリズムをとったり、椅子を動かしたりする音が床を通じて響いてしまうケースがあります。
このような音の種類は、床や壁など固体が振動することで耳に届く「固体伝播音」に分類されます。主にマンションやアパートでは、振動が外側に伝わらないよう防振工事を同時に行うのが重要になります。
楽器演奏だけでなく、例えばオーディオルームやシアタールームとして使用する場合も、スピーカーから発生する振動に注意しましょう。
注意点を踏まえて、自分に合った防音室を導入しよう

防音室を導入する際の注意点についてご紹介しました。
防音室は自宅での楽器演奏やゲームなど、様々な活動を快適にしてくれる一方で、コストや性能の面で考慮すべき点も少なくありません。
導入を検討する際には、メリットだけでなく注意点もきちんと理解した上で、自分のライフスタイルや目的に合った選択をしましょう。
また、可能であれば、まずはショールームに足を運んで、防音性能や居心地を実際に体感してみるのがおすすめです。
自分に合った環境を選ぶことが何よりも大切ですので、事前にしっかりと準備して、後悔のない防音室作りを目指しましょう。
なお、防音対策には防音室だけでなく、吸音パネルやパーティションなど、設置が簡単で優れた効果を発揮するものもあります。
壁に取り付けるタイプや、テレワークスペースとしてデスク周りに設置するものなど用途も様々で、折りたたみ式で広げて使えるものもありますので収納にも便利です。
簡易的な防音対策を考えているという方は、手軽に使える防音グッズも検討してみると良いでしょう。
宮地楽器が提供する吸音・消音性抜群の簡易防音室・防音パネルブランド「VERY-Q(ベリーク)」は一般企業の方々や、楽器演奏などを楽しむ方々に導入していただいている実績を活かし、防音対策の新たな形をご提案しております。
防音ボックスや吸音パネルなど、防音対策に便利な製品を多数扱っておりますので、まずはお気軽にお問い合わせ・ご相談ください。