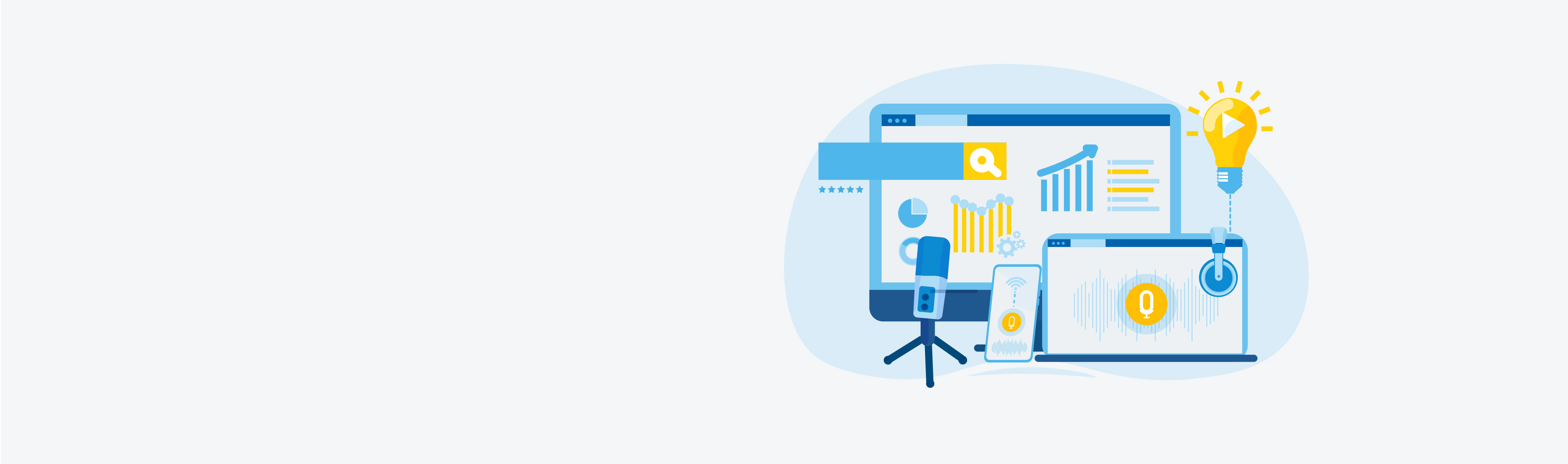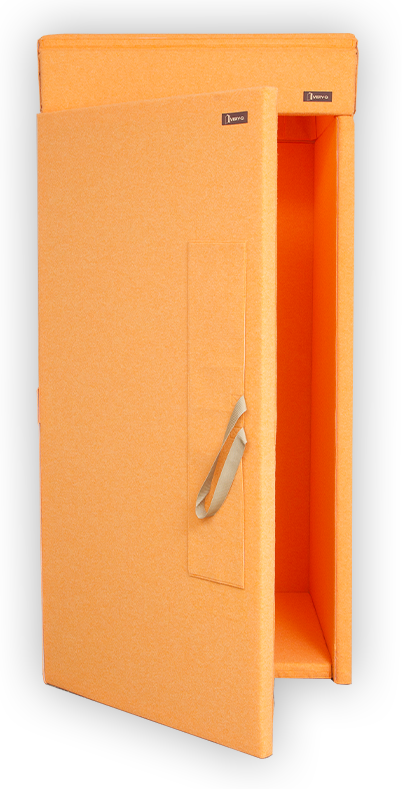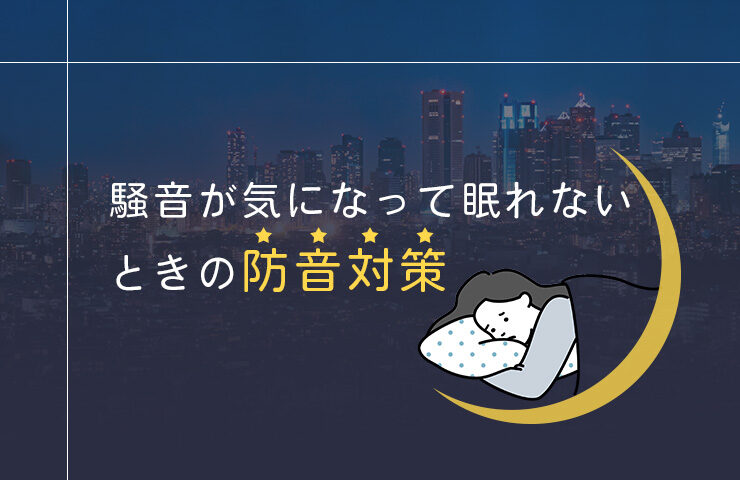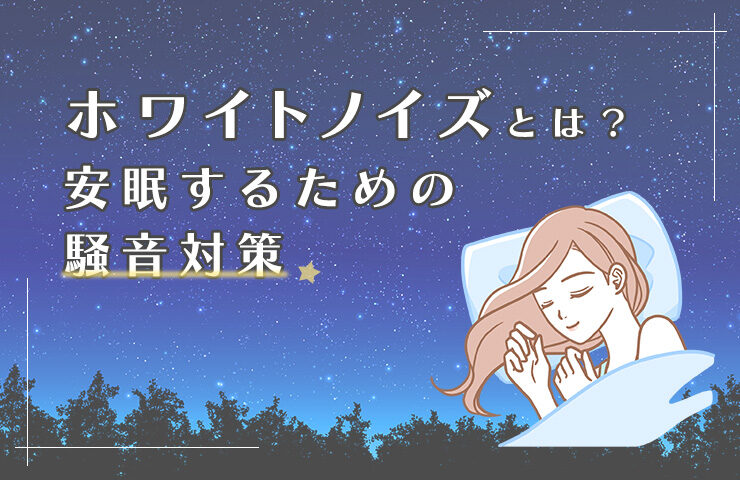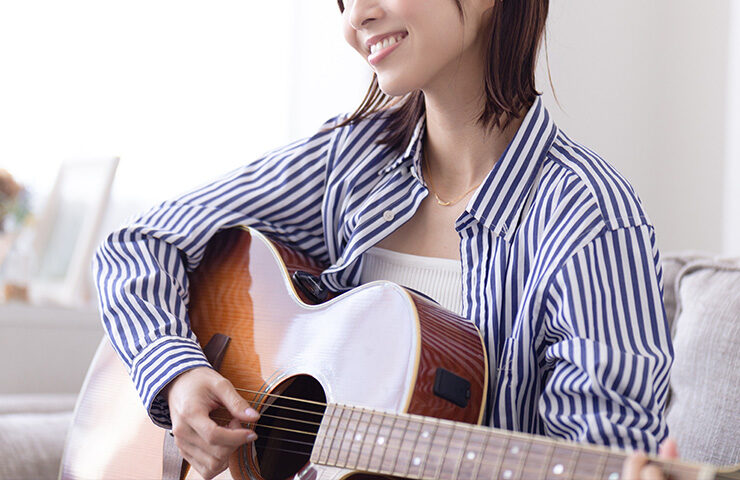音楽療法士になるためには? 必要なスキルや仕事内容について

リズムの良い音楽を聴くと元気が出たり、思い出の歌を耳にすると気持ちが過去に戻ったりするような感覚を味わったことは、誰でも一度は経験があるのではないでしょうか?
このような音楽の力を専門的に活用して、人の身体や心のリズムを整えていく職業に「音楽療法士」というものがあります。
今回は、音楽療法士の仕事内容や求められるスキル、働き方について解説していきます。
音楽療法士とは?
音楽療法士は、音楽の力を使って人の身体と心の状態を整える専門家で、目的や理論に基づいて、利用者の気持ちや状態に寄り添いながら生活の支援をしていく仕事です。
例えば、認知症の高齢者と昔の童謡を一緒に歌って記憶を引き出したり、発達障害のある子どもにリズムに合わせて身体を動かしてもらって自己表現のサポートをしたりします。
また、精神的に落ち込んでいる人に対して、楽器の音色や歌詞を通して感情を外に出す機会を作るなども役割の一つです。
そのため、音楽の知識や演奏スキルだけでなく、心理学や医療、福祉の知識、そして人の気持ちに寄り添える力が求められます。
音楽療法士に必要なスキル
音楽療法士としての活動は、「音楽が好き」というだけでは務まらず、音楽以外の知識やコミュニケーション能力などのスキルが求められます。
・演奏スキルと音楽理論の基礎
音楽療法士にとって、もちろん音楽的なスキルは欠かせず、ピアノやギターなどの楽器を扱う技術や、楽譜を読んだり、即興演奏ができたりする能力、そして利用者の様子を見ながら曲のテンポやキーを変える柔軟性が必要になります。
利用者の反応がその日の体調によって異なるケースも多く、突然テンションが上がったり、落ち着かなくなったりした場合に対応できる力も大切です。
・心理、福祉、教育に関する基礎知識
音楽療法は医療や福祉、心理、教育の現場と密接につながっており、心理学や医学的知識、障害特性の理解なども必要です。
例えば、発達障害を抱える子どもには感覚の過敏さや特性の理解、認知症の高齢者には医学的な視点が求められます。
また、精神疾患を抱える利用者と接する際には、言葉の選び方や距離感にも注意しなければなりません。
・共感と信頼関係を築く対人関係スキル
どんなに音楽が上手でも、利用者の心に寄り添えなければ音楽療法は成立しません。
音楽療法の利用者は、体調や気持ちが不安定だったり、過去に傷を抱えていたりすることが珍しくありません。
そのため、沈黙に寄り添い、笑顔やうなずきで安心感を与えるといった関わり方がとても大切なのです。
心理的な距離のとり方、言葉のかけ方、表情や声のトーンなど、全身を使って利用者との信頼関係を築いていく姿勢も重要です。
音楽療法士になるための準備と学習方法
日本では、音楽療法士の国家資格は存在しませんが(2025年4月時点)、主に「日本音楽療法学会」や「全国音楽療法士養成協議会」が資格認定を行っており、資格を持っている人は病院や介護施設、特別支援学校などの現場で活躍しています。
・「日本音楽療法学会」と「全国音楽療法士養成協議会」が認定する資格の取得
音楽療法士の資格で、高く評価されているのが「日本音楽療法学会」が認定する資格です。
この学会の資格を取得するには、資格試験受験認定校に入学、もしくは必修講習会に参加したうえで、「音楽療法士(補)試験」と「面接試験」に合格する必要があります。
また、同様に評価の高い「全国音楽療法士養成協議会」が定める資格制度は、「専修」「一種」「二種」と3つの区分があり、音楽療法士養成課程のある教育機関を卒業すれば認定されます。
・現場での実習やボランティア経験を積む
在学中から積極的に現場に足を運び、ボランティアやインターンなどを通じてリアルな空気を肌で感じておくのもおすすめです。
例えば、認知症ケア施設や障害児支援センター、児童館、ホスピス、小児病棟などで音楽を用いた活動に参加すると、対象者のリアルな反応や関係性の築き方を学べるでしょう。
音楽療法士としての働き方は?

音楽療法士になったあとに、実際にどのような場所で、どのような働き方をするのかをしっかりイメージしておくのは、将来を考えるうえでとても重要です。
・医療現場で「治療補助」としてチームに関わる
病院やクリニックなどの医療機関では、音楽療法士はリハビリテーションや精神科ケアの一環としてチームに加わります。
例えば、脳梗塞後のリハビリ患者に対して、音楽のリズムを使って身体の動きを引き出す「リズム歩行訓練」を行ったり、うつ病や統合失調症の患者に対しては、歌唱や作詞作曲を通じて内面の感情を整理する支援をしたりします。
医療現場では、医師や看護師、作業療法士、理学療法士、臨床心理士など他職種と連携してチーム医療を行うのが基本で、医療リテラシーを持った専門職としての役割が求められます。
・福祉、介護分野で日常に音楽を取り入れるサポート
介護老人保健施設(老健)や特別養護老人ホームなどでは、認知症ケアや身体機能維持の一環として音楽療法を取り入れている施設が多いです。
懐かしい歌謡曲を一緒に歌って記憶を引き出す回想療法、手拍子やタンバリンを使った簡単なリズム運動、楽器を用いた集団活動をメインに実施します。
福祉施設でのセッションは、治療を目的とするよりも、「生活の質を上げる」「本人らしさを取り戻す」といった目的が強く、介護職や生活支援員と協力しながら、入所者の日常に自然と溶け込む音楽の時間を作り出していきます。
・教育分野で発達支援や情緒安定の支えになる
特別支援学校や発達支援センター、放課後等デイサービスなどの教育、発達支援分野でも、音楽療法士のニーズは高まっています。
言葉でのコミュニケーションが難しかったり、感覚が過敏だったりする子どもに対して、音楽を通して感情表現や身体の動きをコントロールする方法を教え、他者との関わりを学ぶ手助けをする役割を担う場合が多いです。
保育士や施設の従業員、学校の先生とも連携を取りながら支援をしていきます。
・フリーランスとしての独立や兼業スタイルも増加中
最近では、施設や病院に勤めるだけでなく、フリーランスとして活動する音楽療法士も増えています。
例えば、自分で音楽療法の教室を開く、複数の施設と契約してセッションを提供する、イベントや企業研修に呼ばれてワークショップを行うなど、活動できる幅が広がってきました。
また、音楽講師やピアノ教師との兼業、カウンセラーやコーチングとの組み合わせ、YouTubeやSNSでの情報発信など、個人の得意分野やライフスタイルに合わせた働き方が可能です。
音楽療法と防音対策について
音楽療法のセッションでは、音漏れや騒音といった環境音にも気をつけなければなりません。
特にマンションなど、自宅で演奏を行う音楽療法では、防音対策ができていないと集中して取り組めないというケースも少なくありません。
防音対策は、窓やドアのすき間に防音テープを貼るだけで、外への音漏れがかなり軽減されます。
また、壁に吸音パネルやカーテンを使って反響音を抑えたり、床に厚手のマットを敷いたりすると、足音や楽器の振動が伝わりにくくなります。
さらに、安心して心置きなくセッションを行うためには、簡易的な防音室の設置や、本格的な防音工事を検討してみるのも良いでしょう。
音楽療法において音は最大の武器ですが、扱い方次第では周囲にとって騒音にもなりうる要素です。
音環境を整えるのは、近隣住民はもちろん、利用者と音楽療法士が安心して支援を進めるために不可欠なので必ず対策をしましょう。
音楽を通じて人に寄り添う「音楽療法士」を目指してみよう

音楽療法士は音楽が好きなだけでなく、利用者の気持ちを理解し、安心できる空間を整えていく繊細なスキルと優しさが求められる仕事です。
自身の音楽で他人の人生に寄り添い、役に立ちたいという人にとっては、とても大きなやり甲斐があるでしょう。
もしも興味があれば、まずは情報を集めて興味のある学校を調べたり、実際の現場を見学してみたりと、ぜひ小さな行動から始めてみて下さい!